いきなりですが、「合気道の体術」という題名にしましたが、体術の捉え方は道場によって異なる部分も多いため、彦根道場長独自の見解だという意識でお読みください。
私は、体術には以下の役割が有ると思っています。
- 無手に対する格闘技的な役割
- 短刀の技術習得の役割
- 短刀取りを習得するための役割
- 剣術を補完する役割
- 剣術技術習得のための役割
- 無刀取り習得のための役割
- 杖術を補完するための役割
- 杖術技術習得のための役割
- 杖取り習得のための役割
体術の役割の大半が武器術の習得、または武器技の補完を目的としたものであると思うのです。
具体的に説明すると。
上記の番号1番は 素手対素手の武道としての体術です
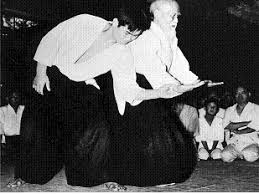
「 体術 」は非常に範囲が広く、格闘から戦闘 まで色々とあるようです。
よく「合気道が使えるか?」のような議論になるのは、体術の格闘技的な部分の話だろうと思います。
個人的には、合気道は格闘技には利用が難しいだろうと思います。
合気道の基になった古武道の時代では、今のような格闘スタイルでは無かったためです。
どちらかと言えば合戦場のような世界で使うのが目的の武道でしょうか。
2番・5番・8番は、武器術の技術習得の目的

木刀 や 木杖 、 木製短刀を利用して、本気の稽古は不可能です。真剣ほどの殺傷力は無いものの、それでも、まともに当たれば大怪我は避けられないでしょう。
そこで、無手で稽古を行います。
これなら本気で稽古をしても大怪我は致しませんね。
もしかして、柳生石舟斎 が無刀取りを習得した稽古方法は、徒手での本気の稽古だったのでは無いかと思います。
合気道は「 剣を持たない剣の稽古 」というのは、本当にそのままの意味だろうと思います。
この言葉どおりに稽古をするには、武器技のつもりで体術を稽古する必要が有ります。
だからこそ、無手で武器技の稽古 をするためにも、まずは、武器を使った武器技稽古を修めなければならないと思います。
4番・7番は、 武器技を補完する目的

武器を持っている時に、相手に掴まれて動きを封じられた場合に利用するという役割です。
呼吸法などの体術を利用し、捕縛してきた相手を崩しながら攻めていく事が必要です。
戦場では 多対一 が基本です。一瞬動きを止められてしまう程度であっても致命傷に繋がります。
動きを封じられたら、体術で上手くカバーします。
武器技を活かすための体術 ということですね。
3・6・9番、 武器を奪う目的

武器が無い場合は敵から調達する。
これは大変難しいですが、合戦場での活躍を意識した武道体系を考えた場合、必須の技術と言えるでしょう。
前出の無刀取りは、ここに位置する技術だと思います。
構造を理解して稽古する事が大切
個人的な見解ですが、合気道の体術の持つ役割を考えてみました。
わりと色々な目的がありますね。
どの役割も合気道という武道の構造をしっかり理解して、体術の位置づけをよく考えながら稽古をしていきたいと思います。
丁寧に研究していけば、もっと理にかなった合気道体術に辿り着けるかもしれません。
| 稽古曜日 | 稽古時間・場所 |
|---|---|
| 火曜日 【初心者向け】 | 20:00~21:00 彦根市京町道場 |
| 水曜日 | 20:00~21:00 彦根市京町道場 |
| 木曜日 【初心者向け】 | 19:00~20:00 彦根市京町道場 ※この日だけ開始時間が早いです。 |
| 金曜日 【初心者向け】 | 20:00~21:00 彦根市京町道場 |
| 土曜日 | 20:00~21:00 彦根市京町道場 |
| 日曜日 | 14:00~14:50 剣術・杖術クラス イオンモール草津 合気剣・合気杖 14:50~15:45 体術クラス イオンモール草津 合気道体術 ※イオンモール草津の講座は、直接十字屋さんへお申込みください。 20:00~21:00 彦根市京町道場 |